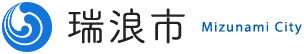桜堂薬師句額群(さくらどうやくしくがくぐん)
桜堂薬師は山号を瑞桜山、寺名を法妙寺(法明寺)といい、土岐町桜堂に所在するかつての天台宗寺院です。
寺伝によれば、平安時代の弘仁3年(812年)三諦上人によって創建され、三諦上人が嵯峨天皇の病気平癒に功績があったことから勅願寺となるも、戦国時代の元亀2年(1571年)織田信長の命を受けた森長可によって焼き討ちされた、と伝えられます。その後、江戸時代、比叡山から桜堂薬師に入った永秀と弟子の賢秀、また当地を治めた岩村藩の援助によって再興され、現在まで法灯が受け継がれています。
桜堂薬師では、江戸時代から明治時代にかけて句会(俳諧を読み、お互いに批評する集まり)が催されていたようで、本堂にはその際に奉納された句額(俳諧を記した額)が多く残されており、宝暦句額、寛政句額、弘化句額の3面が文化財に指定されています。
宝暦句額と寛政句額は、当市における俳諧の第1次隆盛期(宝暦~寛政年間:18世紀後半)、弘化句額は第2次隆盛期(安政~慶応年間:19世紀中頃)を示すものですが、このような句会が催された経緯からは、当時の桜堂薬師が、いわば当地の文化サロンとして認識されていたことがうかがわれます。
宝暦句額

宝暦5年(1755年)、釜戸の俳人安藤松軒(範高)が蓮阿坊白尼、五条坊木児、五竹坊東伯など、尾張・美濃から多くの俳人を招いて大句会を催した際に奉納したものです。桜堂薬師に因んで「桜」を題材にした約40首が詠まれているとされますが、退色が進んでいるため文字の判読は困難です。
安藤松軒は現在の釜戸町大島に住み、代々医者として領主の馬場氏に仕えたと言われています。松軒は医業の傍ら俳諧をたしなみ、「竃山人」とも号して、東濃における俳諧の中心人物として活躍しました。
寛政句額

宝暦句会から30余年後の寛政3年(1791年)、再び桜堂薬師で大句会が催された際に奉納されたものです。宝暦句額を奉納した安藤松軒(範高)の子、二代松軒(範倶)が中心となり、市内各村々、また県内及び県外からの参加者が約210句を奉納しました。
この句会の中心人物である二代松軒は「白兔」とも号し、初代松軒とともに当市における俳諧の第1次隆盛期を築いた人物です。この他、寛政10年(1798年)には芭蕉の百年忌供養のため、釜戸町宿に「此のあたり 目に見ゆるもの 皆涼し」の俳聖句碑を造立しています。
弘化句額

弘化2年(1845年)に奉納された句額で、他の句額とは異なり冒頭に桜堂薬師の由来を記し、6首の連歌と約20首の俳諧が詠まれています。末尾にある願主の「龍翔」は美濃派の流れをくむ俳人と推察されますが、詳細は不明です。
なお、美濃派とは俳諧流派の一つで、各務支考を創始者とします。支考は元禄の頃に松尾芭蕉の門下に入り才能を認められ、蕉門十哲(芭蕉の特に優れた高弟10人)の一人にも数えられた俳人です。
- 指定番号
- 瑞有28
- 指定年月日
- 昭和57年11月17日
- 指定の別
- 市指定文化財
- 種別
- 有形文化財
- 類別
- 書跡
- 時代・年代
- 江戸時代
- 員数他
- 3枚
- 所在地
- 瑞浪市土岐町5728番地 桜堂薬師
- 所有者・管理者又は技術保持者
- 桜堂薬師
このページに関するお問い合わせ
みずなみ未来部 スポーツ文化課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
歴史文化係 化石博物館 電話:0572-68-7710
歴史文化係 市之瀬廣太記念美術館 電話:0572-68-9400
歴史文化係 陶磁資料館 電話:0572-67-2506
スポーツ推進係 市民体育館 電話:0572-68-0747