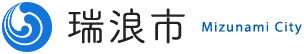光春院の慶応句額群(こうしゅんいんのけいおうくがくぐん)

光春院は、山号を定林山、寺号を光春院といい、瑞浪市釜戸町公文垣内に所在する臨済宗の寺院です。江戸時代の慶長16年(1611年)に創建、元禄5年(1692年)に再興されたと言われています。
瑞浪市域では、江戸時代になると庶民文芸として俳句や俳諧が流行し、宝暦年間(1751年~1763年)頃、また安政・慶応年間(1854年~1868年)頃に隆盛を迎えましたが、幕末期に光春院の住職であった売仏は、号を風意軒と称して、当時の俳諧の中心的な人物でした。
これらの句額群は、慶応4年(1868年)に売仏が花輪らと光春院で大句会を催した際に奉納されたもので、参加した37名の句と、作者とみられる肖像画が彩色豊かに描かれています。
句額はいずれも高さ34センチメートル、幅26センチメートルですが、願主である花輪の句額のみ高さが58センチメートルと大型で、主催者であった2人の句は以下のとおりです。
阿だつは どじょうのあくびや ぬるみ水 売仏
馬買った あかしの路や きりぎりす 花輪
なお、売仏は文化7年(1810年)~明治9年(1876年)の人物で、安政2年(1855年)に出版された俳諧全国誌「竹の春」にも以下の句が選ばれており、全国レベルの俳諧人として知られていたようです。
久かたの 光や松の 月高し 濃州釜戸 売仏
- 指定番号
- 瑞有23
- 指定年月日
- 昭和54年3月2日
- 指定の別
- 市指定文化財
- 種別
- 有形文化財
- 類別
- 書跡
- 時代・年代
- 慶応4年(1868年)
- 員数他
- 37面
- 所在地
- 瑞浪市釜戸町580番地の2
- 所有者・管理者又は技術保持者
- 光春院
このページに関するお問い合わせ
みずなみ未来部 スポーツ文化課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
歴史文化係 化石博物館 電話:0572-68-7710
歴史文化係 市之瀬廣太記念美術館 電話:0572-68-9400
歴史文化係 陶磁資料館 電話:0572-67-2506
スポーツ推進係 市民体育館 電話:0572-68-0747