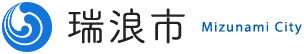住宅改修費支給申請
事務・手続名
住宅改修費支給申請
概要
要介護(支援)認定者が、介護保険で規定されている住宅改修を行う際に、住宅改修費を受給するための手続きです。
着工前の事前申請と、改修後の事後申請の両方が必要です。
(注)事前申請後に、市が改修を承認。承認前に改修した場合は、申請不可。
(注)承認を受けた上で、入院(又は入所)中に住宅改修を行った場合は、退院(又は退所)後に事後申請可。(退院するまでは事後申請不可)
(注)本人又は家族等が住宅改修を行う場合は、材料の購入費のみ支給対象とする。なお、この場合であっても必要となる書類は同じ。
(注)同一の住宅について、同時に複数の被保険者に係る住宅改修が行われる場合は、各被保険者に有意な範囲を特定し、その範囲が重複しないように申請を行うものとする。(例:共用の居室において床材の変更を行ったときは、いずれか一方のみが申請を行う)
(注)住宅改修費支給申請(事後申請)の消滅時効は、被保険者が施行業者に代金を完済した日(領収日)の翌日から起算して2年。
介護保険の給付対象となる住宅改修
次の住宅改修のうち、厚生労働大臣が定める基準を満たすもの
手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。なお、福祉用具貸与における「手すり」に該当するものは除かれる。
段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室のかさ上げ等が想定される。ただし、福祉用具貸与における「スロープ」又は特定福祉用具販売における「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。
また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定される。
引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、保険給付の対象とならない。
洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する場合が一般的に想定される。
ただし、特定福祉用具販売における「腰掛便座」の設置は除かれる。
また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は保険給付の対象とならない。
その他、上記に付帯して必要となる住宅改修
- 手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強 - 段差の解消
浴室の床の段差解消(浴室のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置 - 床又は通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備 - 扉の取替え
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 - 便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更
介護保険の給付対象とならない場合(主な例)
- 被保険者が居住しない住宅又は住所地でない住宅の場合
- 被保険者の心身状況等から勘案して、必要と認められない場合
- 事前申請かつ承認を受ける前に着工した場合
- 改修後、入院等の事情で被保険者が在宅で生活されない場合(退院、退所後に在宅で生活された場合は支給可)
- 住宅改修を伴わない設計及び積算のみの場合
- 住宅の新築の場合
- 住宅の増築の場合で、新たに居室を設ける場合等
支給限度額
申請額の上限は20万円(支給額の上限は18万円、16万円、又は14万円)
(注)限度額の範囲内であれば、複数回に分けて申請可。
(注)最初に住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工時点と比較して、「介護の必要の程度」(下表のとおり)が3段階以上上がった場合は、改めて20万円まで申請可。なお、この取扱いは1回に限られる。
(注)転居した場合(前回、支給を受けた住宅以外の住宅において住宅改修をした場合)は、改めて20万円まで申請可。
(注)同一の住宅に複数の被保険者がいる場合は、被保険者ごとに支給限度額を管理する。
| 「介護の必要の程度」の段階 | 要介護等状態区分 |
|---|---|
| 第1段階 | 要支援1 |
| 第2段階 | 要支援2又は要介護1 |
| 第3段階 | 要介護2 |
| 第4段階 | 要介護3 |
| 第5段階 | 要介護4 |
| 第6段階 | 要介護5 |
手続きに必要なもの
着工前(事前申請)に必要な書類
- 住宅改修費支給申請書
- 承諾書(住宅の所有者が被保険者でない場合のみ)
- 委任状(振込先口座が被保険者名義でない場合のみ)
- 住宅改修が必要な理由書 (注)担当の介護支援専門員が作成
- 改修費の見積書 (注)施行業者が作成
- 着工前の写真(日付入りのもの)
- 改修後の状態がわかるもの(イメージ図等) (注)施行業者が作成
- 平面図(生活動線を記したもの) (注)施行業者が作成
マイナンバー関連で提示が必要なもの
被保険者本人が申請する場合
- 被保険者の通知カード又は個人番号カード等 (注)提示が困難な場合は提示不要(保険者による番号確認)
- 被保険者の運転免許証等を1点又は医療保険被保険者証等を2点 (注)上記1で個人番号カードを提示する場合は不要
代理人が申請する場合
- 被保険者の通知カード(又は写し)又は個人番号カード(又は写し)等 (注)提示が困難な場合は提示不要(保険者による番号確認)
- 委任状又は被保険者の介護保険被保険者証等
- 代理人の運転免許証等を1点又は医療保険被保険者証等を2点
代理権の無い使者が申請する場合
- 被保険者の通知カード(又は写し)又は個人番号カード(又は写し)等 (注)提示が困難な場合は提示不要(保険者による番号確認)
- 被保険者の運転免許証(又は写し)等を1点又は医療保険被保険者証(又は写し)等を2点 (注)上記1で個人番号カード(又は写し)を提示する場合は不要
改修後(事後申請)に必要な書類
- 領収書(原本) (注)確認後、申請者に返還 (注)家族等が改修した場合は、材料を販売した店が発行した領収書が必要
- 改修費の内訳書(着工日及び完了日の記載があるもの) (注)施行業者が作成 (注)家族等が改修した場合は、家族等が作成した内訳書が必要
- 改修後の写真(日付入りのもの)
注意事項
書式
-
住宅改修見積書標準様式 (Excel 15.1KB)

-
住宅改修費支給申請書 (PDF 65.8KB)

-
住宅改修費支給及び事前審査申請書(受領委任払用) (PDF 114.4KB)

-
承諾書(住宅改修費) (PDF 56.0KB)

-
承諾書(住宅改修費・所有者死亡の場合) (PDF 68.5KB)

-
委任状(住宅改修費の代理受領) (PDF 39.9KB)

-
委任状(マイナンバー制度における代理権の確認) (PDF 53.9KB)

よくある質問
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117