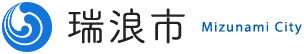中山道を歩く
お役立ち情報
中山道・東海自然歩道中の施設等に関する情報は下記よりご覧ください。
観光スポット
-
 中山道
中山道
瑞浪市の北部丘陵を東西に中山道が通り、街道筋には大湫宿、細久手宿、一里塚、石畳が残る琵琶峠、十三峠、弁財天の池など多くの史跡や名所があります。街道のほとんどが東海自然歩道としても整備され、四季を通じてたくさんのウォーカーが訪れます。 - 中山道観光ボランティアガイドの申込
-
 大湫宿
大湫宿
大湫宿は江戸から47番目の宿として、海抜510mの高地に設けられ、江戸へ90里半、京都へ43里半、東隣りの大井宿へ3里半、西隣の細久手宿へ1里半、美濃16宿の中で最高所に位置し、それだけ急坂が続いており、旅人も人馬役からも難所とされていました。 -
 大湫宿旧森川訓行家住宅(丸森)
大湫宿旧森川訓行家住宅(丸森)
旧森川訓行家住宅は、中山道大湫宿の北部に位置し、一族の中でも各々を区別するために「丸森」と呼ばれ、旅籠屋の他に尾州藩の許可を得て塩の専売も行い、繁盛を極めたとされています。 -
 観音堂
観音堂
かつての宿場町西側の高台に所在する観音堂で、難病平癒(特に足の病)や道中加護のご利益があると言われ、現在も地域住民の信仰を集めています。享保6年(1721年)に現在地へ移され、弘化4年(1847年)に再建されたことなどが記されています。観音堂の絵天井は、弘化4年(1847年)、恵那郡付知村の画人三尾静(暁峰)の作で、花鳥草木を主に板絵60枚が描かれています。 -
 細久手宿
細久手宿
細久手宿は江戸から48番目の宿で、江戸へ92里、京都へ42里の位置にあり、東隣りの大湫宿と西隣りの御嶽宿の両宿間は4里半と長く、両宿の人馬が難渋したため、慶長11年(1606年)に仮宿を設けたのが始まりです。宿内の町並みは東高西低で、東の茶屋ヶ根から西の日吉・愛宕神社入口迄が上町・中町・下町に三分され、宿長は3町45間(410メートル)ありました。 -
 大黒屋旅館
大黒屋旅館
尾州家定本陣でいまも料理旅館を営んでいます。本卯建・玄関門・式台・上段の間なども往時のままに残っています。 -
 庚申堂
庚申堂
宝暦以来の小堂宇を寛政10年(1798年)の宿中大火のあと、宿の鬼門除けとして享和2年(1802年)に再建したものです。宿内はもちろん近郷や旅人からも「細久手宿のこうしんさま」として親しまれたお堂で、ここからは宿内が一望できます。 -
 十三峠
十三峠
中山道大湫宿と大井宿の間の十三峠は、その名のとおり起伏が激しく、難所とされていました。この区間には、三十三所観音、権現山一里塚、尻冷やし地蔵、樫ノ木坂の石畳など多くの史跡が残っています。 -
 琵琶峠
琵琶峠
琵琶峠は麓からの実高80メートル・長さ1キロメートルで、中山道美濃・近江路で最も高い峠です。700メートル余りにわたって石畳がしかれており、頂上直下には八瀬沢一里塚が残っています。往時から木曽街道六拾九次や木曽路名所図会にも描かれた中山道の名所です。 -
 一里塚
一里塚
瑞浪市内の中山道には、昔のままの姿で一里塚が残っています。東から、権現山一里塚、八瀬沢一里塚、奥之田一里塚、鴨之巣一里塚で、連続して4ヶ所もの一里塚が残っている例は全国的にもまれです。 -
 弁財天の池
弁財天の池
大湫宿と細久手宿の中間に位置し、太田南畝の「壬戌紀行」にも「小さき池あり・杜若(かきつばた)生ひしげれり・池の中に弁財天の宮あり」と記述された750平方メートルほどの浅い池で、小島に天保7年(1836年)に再建された石祠があります。浅い池ですが、水を絶やすことなく初夏にはカキツバタが美しい花を咲かせています。