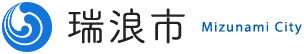未来と自然プロジェクト研究
このプロジェクト研究では、10名の参加者が、事業構想大学院大学の講師によるノウハウの詰まった全19回のカリキュラムを受講し、令和7年1月には、瑞浪市の発展、課題解決につながる事業構想を1人1つ創り上げます。

未来と自然プロジェクト研究 開始
第1回(6月28日)
講義内容
オリエンテーション
事業構想概論
問題の捉え方と課題抽出へのアプローチ
担当講師より、事業構想大学院大学の研究生の証である任命証が手渡されました。
顔合わせとなる第1回は、自己紹介に始まり、このプロジェクトに携わる想いをそれぞれが語りました。

第2回(7月12日)
講義内容
地方創生に関する講義
瑞浪市役所からの市の現状プレゼンテーション
市役所職員に対する現状への質疑応答
人口、経済の2面から地方創生の考え方について学び、国の施策の方向性やRESAS(地域経済分析システム)を活用したデータの取得、分析など今後の課題分析の基礎となる知識を習得しました。また、瑞浪市からは担当職員より第7次瑞浪市総合計画の概要を説明しました。総合計画の策定にあたっての市民意見の聴取結果や、そこから見出した課題を踏まえた説明をし、参加者との意見交換を行いました。

第3回(7月26日)
講義内容
クリエィティブ発想法
クリエイティブ発想ワークショップ
今回は、日本ガイシ株式会社(名古屋市)を訪問し、常設技術展示場をお借りして講義が行われました。物事を見る際にはバイアスがかかることを前提に、物事を捉えなければならないことを学びました。また、日本ガイシ株式会社の取り組みを紹介いただくなかで、DACやサブナノセラミックスの製品開発など、新たなビジネス創出による利潤確保とそれによる社会貢献の持続化の両立を目指していることを知りました。

第4回(8月2日)
講義内容
マーケティング論
課題発見ワークショップ
今回は、事業構想大学院大学名古屋校(名古屋市)にて講義が行われました。
帰納的思考、演繹(えんえき)的思考、アナロジー、アブダクションなど、事実から結論を導き出す考え方を学びました。これらの考え方を踏まえ、起こっている事象から原因を推測し、この先何が起こりうるのか、その先にあるべき理想像を考える練習を行いました。

第5回(8月9日)
講義内容
瑞浪市のフィールドリサーチ
フィールドリサーチの内容のまとめ方
様々な分野でどんな課題を抱えているのか。実際に事業所や団体をまわり、関係者の方から聞き取りを行いました。
現場に携わる方々に直接お話を聞くことで、実情がよく分かり、今後、課題解決に向けた構想を考える上での参考になりました。
<フィールドリサーチ先>
Aグループ 大湫町まちづくり推進協議会、カマドブリュワリー
Bグループ 農事組合法人 日吉機械化営農組合、日吉町まちづくり推進協議会、稲津地域子育て支援センター(おんぶにだっこ)
上記ほかA,Bグループ共通 瑞浪駅周辺再開発事業、ミライ創ろまい課のお話

第6回(8月23日)
講義内容
SDGs概論・公民共創
瑞浪市の問題・課題のディスカッションと共有
SDGsとは何か、なぜSDGsが世界的に推進されているのかなどの講義を受ける中で、各企業がビジネスにもSDGsの考え方を取り込み、活動がなされていることを学びました。また、公民共創については、「公」と「民」の最近の関わり方について学びました。

第7回(9月6日)
講義内容
研究員がテーマとする瑞浪市の現状(問題)に対するあるべき姿と、そのあるべき姿にたどり着くための課題のプレゼンテーション
各研究員がこれまで講義で学んできたことを活かして、それぞれが思う市の課題をまとめ、その課題の解決に向けたアプローチについて発表しました。
講師の方や他の研究員との意見交換を通して、それぞれのアプローチの方向性を整理しました。
今後、それぞれの想いをさらに深く掘り下げ、構想にまとめていきます。

第8回(9月20日)
講義内容
ビジネスモデル概論
BMC、VPC
ワークショップ
本日は、ビジネスモデル概論についての講義を受けました。BMC(ビジネスモデルキャンパス)、VPC(バリュープロポジションキャンパス)等の考え方や、ビジネスモデルを考える上での、市場の把握と分類(セグメンテーション)、対象となる市場の決定(ターゲティング)、対象市場の自社の位置(ポジショニング)を整理することの重要性を学びました。今後の事業構想立案の根幹を成す部分であるとあらためて認識しました。
また、本日は全19回の講義の半ばを迎え、水野市長が受講の様子を見学し、研究員を激励しました。

第9回(9月27日)
講義内容
DX・RPA・脱炭素・クリーンエネルギーなど各種最新テクノロジー
プレゼンテーションスキル
今回は、「テクノロジーとイノベーション」、「プレゼンテーションスキル」についての講義が行われ、2名の講師からそれぞれの専門分野に関するお話を伺いました。イノベーションの多様な側面や何のために新技術を活用し、技術が進化する中で私たちがどのように変化に適応して利用していくべきかを学びました。また、プレゼンテーションを行う上で必要な人前で話すための準備方法、企画を通すための説得の仕方、効率的なスライド資料の作成について学びました。今回の講義で得た知識や技術を参考に、今後の活動に活かしていきます。
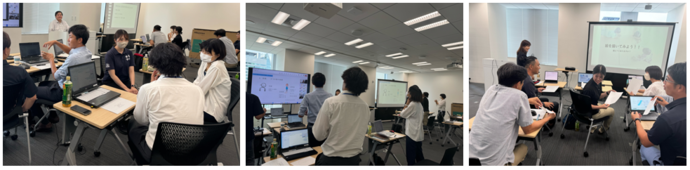
第10回(10月11日)
講義内容
研究員がこの時点で想定している事業構想案を元に様々な視点からディスカッションしブラッシュアップ
それぞれが現時点で考えている事業構想案を元に、数人のグループに分かれて意見交換をし、発表資料だけでは伝えきれない資料に込めた想いをメンバーに伝えることで、色々な視点から意見を言い合うことができました。グループワークでは、令和5年度に長野県富士見町との産官学連携プロジェクトに携わったトヨタ車体株式会社の方にも入っていただき、外部の目線でアドバイスをいただきました。また、柳田講師との個別面談も行われ、事業構想案をさらにブラッシュアップすべく、それぞれが進むべき方向性を整理していきました。
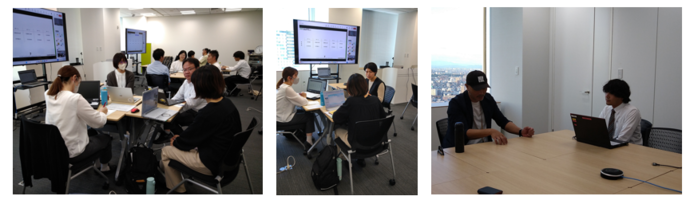
第11回(10月18日)
講義内容
研究員がこの時点で想定している事業構想案を元に様々な視点からディスカッションしブラッシュアップ
前回(第10回)に続き、数人のグループでのグループワーク、その中でトヨタ車体株式会社の方や柳田講師にもアドバイスをいただきました。
次回はいよいよ中間発表となります。これまで11回にわたり学んできたことを活かして、それぞれの考える事業構想の原石を発表します。
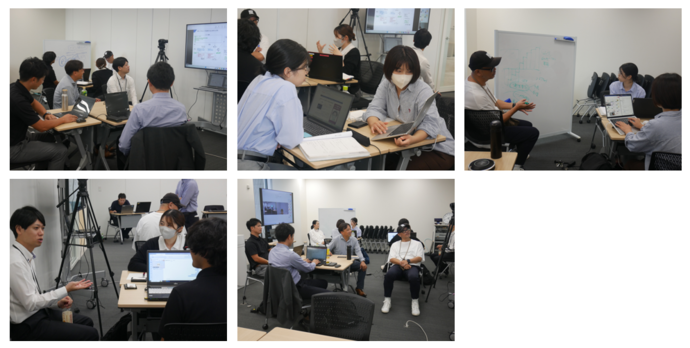
第12回、第13回(11月1日)
講義内容
研究員の事業構想案の中間発表
職員・関係者などの聴講者・関係者からの意見聴取
本日は、それぞれの現時点で想う事業構想の中間発表を行いました。
これまでの11回の講義、ワークショップ等を通して学んできた知識を活かして、それぞれの構想を話しました。発表の内容は、事業構想大学院大学の普段とは違う講師の方や市の幹部職員に聞いていただき、アドバイスや参考事例の紹介等をいただきました。以降、さらにそれぞれの構想をブラッシュアップしていきます。
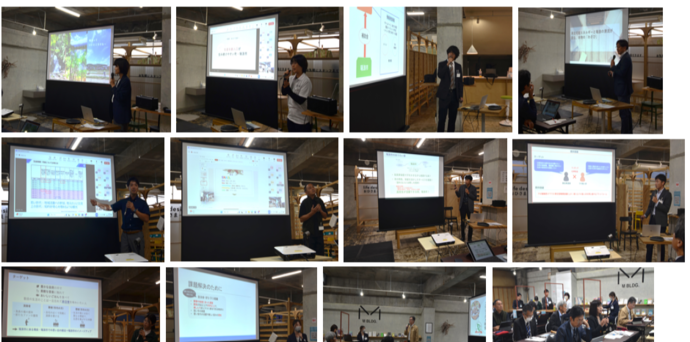
第14回(11月15日)
講義内容
聴講者からのフィードバックを受けた事業構想案の再構築のためのディスカッション
前回の中間発表から、それぞれの構想におけるターゲットのイメージがしっかりとできているか、という点が一つのポイントとしてあげられました。市場調査等から得られる回答者の建前や本音から、表面には現れてこない深層心理をいかに読み解くかが、事業構想を考えるうえで重要となることを学び、それを踏まえて自身の構想をさらに練り上げていきます。

第15回(11月29日)
講義内容
事業構想案再構築のためのディスカッション
収支計算の基礎知識
本日は、損益計算書、変動損益計算書について学びました。これまで大枠で考えてきた事業構想に、収支面で成り立つのか、成り立たせるためにどうすればよいか、コスト計算の視点を盛り込み、それぞれの事業構想をより具体化していきます。

第16回(12月13日)
講義内容
事業構想案の再構築のためのディスカッション
本年最後の講義となりました。事業構想の立案も大詰めを迎え、それぞれの描く構想のターゲットやマーケティングプランを見失わないことが大事であるとのお話をいただきました。
11月の中間発表以降、本日までに変わったところ、より広げたところ、深掘りしたところなどを中心にそれぞれがプレゼンし、意見交換を行いました。
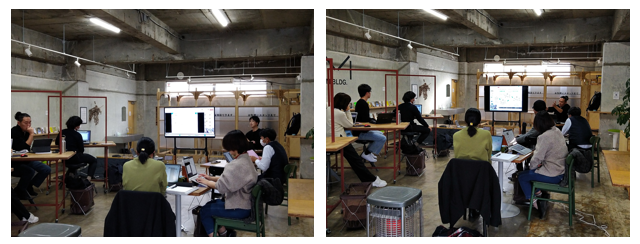
第17回(1月10日)
講義内容
ファイナンスの考え方や収支計画の立て方
ブランディング・IMC概論
本年1回目の講義です。
構想の全体イメージは固まってきましたが、それぞれの構想の実現に向けた収支計画を具体化するため、ファイナンスの考え方、収支計画の立て方について学びました。
第18回(1月24日)
講義内容
事業構想計画の最終調整のためのディスカッション
研究員全員の事業構想の発表(プレプレゼンテーション)
本年1回目の講義です。
最終プレゼンテーションまであと1週間。最終発表に向けたプレゼン資料は概ね完成し、事業構想大学院大学にてプレプレゼンテーションを行いました。
どうプレゼンしたら、聴き手にうまく伝わるかなどを話し合いました。
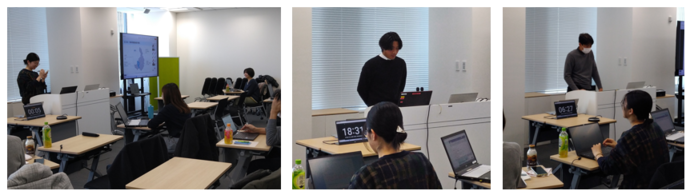
第19回(1月31日)
講義内容
研究員全員の事業構想の発表(最終プレゼンテーション)
いよいよ最終プレゼンテーションの日を迎えました。これまでの講義やフィールドリサーチを通して学んできたことや、それぞれが見つけ出した課題を解決するための事業構想という形にまとめ、約100名の観覧者の前で発表しました。
10人のそれぞれが考えた事業構想は、「瑞浪市をより良くしたい」という熱意が溢れているものばかりで、バラエティに富んだ素晴らしい発表でした。

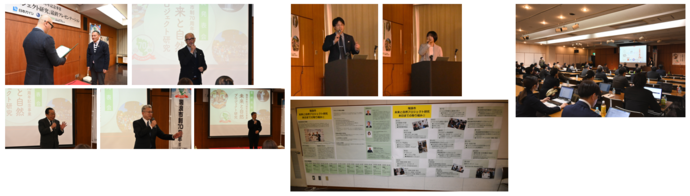
未来と自然プロジェクト研究 参加者を募集します
募集は6月2日をもって終了いたしました。
4月19日、瑞浪市は、日本ガイシ株式会社、学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学と地方創生の推進に関する包括連携協定を締結しました。今後は3者の連携により、地域課題の解決に向けた取り組みを行います。その一環として、日本ガイシ株式会社からの企業版ふるさと納税による寄附を活用し、事業構想大学院大学のノウハウが詰まったカリキュラムを受講しながら、参加者各々が新規事業の構想計画を策定する新たなプロジェクトを開始します。「瑞浪市をより良くしたい」という熱意ある方のご応募をお待ちしております。
参加者募集 説明会
- 5月13日(月曜日)午後6時〜午後7時(Mビル JR瑞浪駅前)
- 5月15日(水曜日)午後1時〜午後2時(オンライン)
- 5月17日(金曜日)午後6時〜午後7時(オンライン)
プログラム概要や修了生の実績等についての説明会を実施します。教員による講義が体験できるようなパートもございますので、ぜひご参加ください。
未来と自然プロジェクト研究の実施に向けて
地方創生の推進に関する包括連携協定の締結

企業版ふるさと納税による寄付

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。